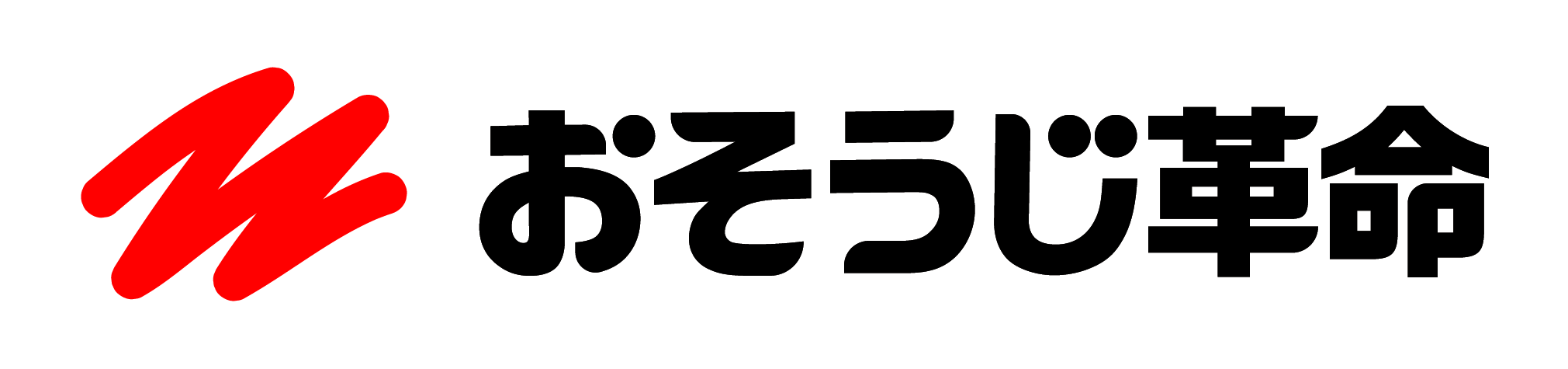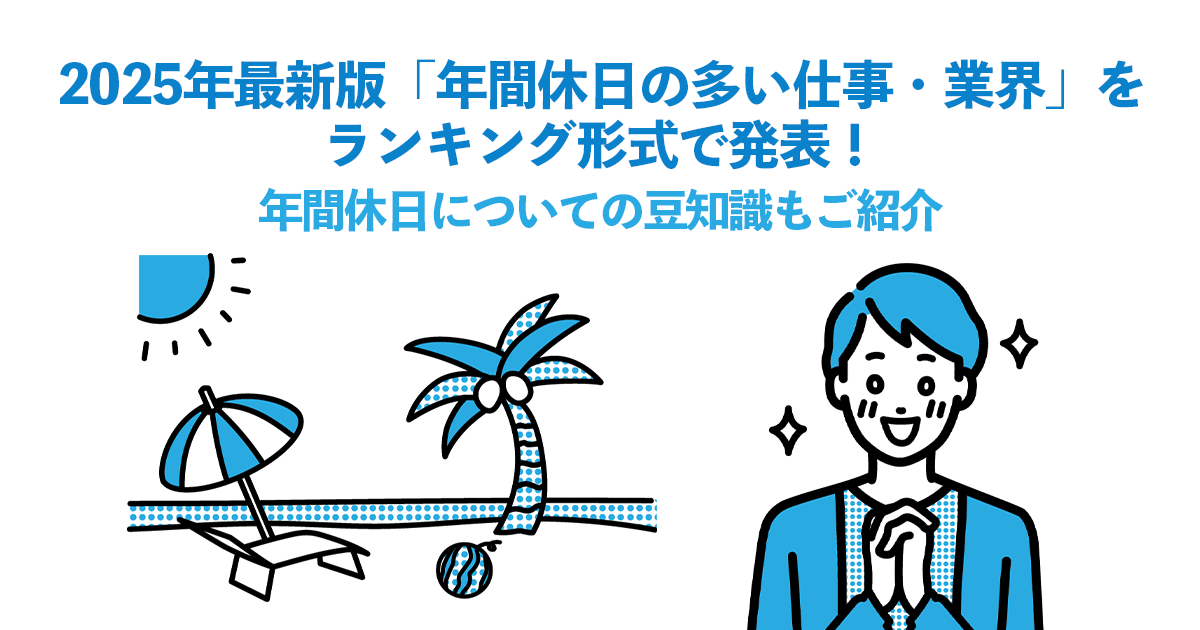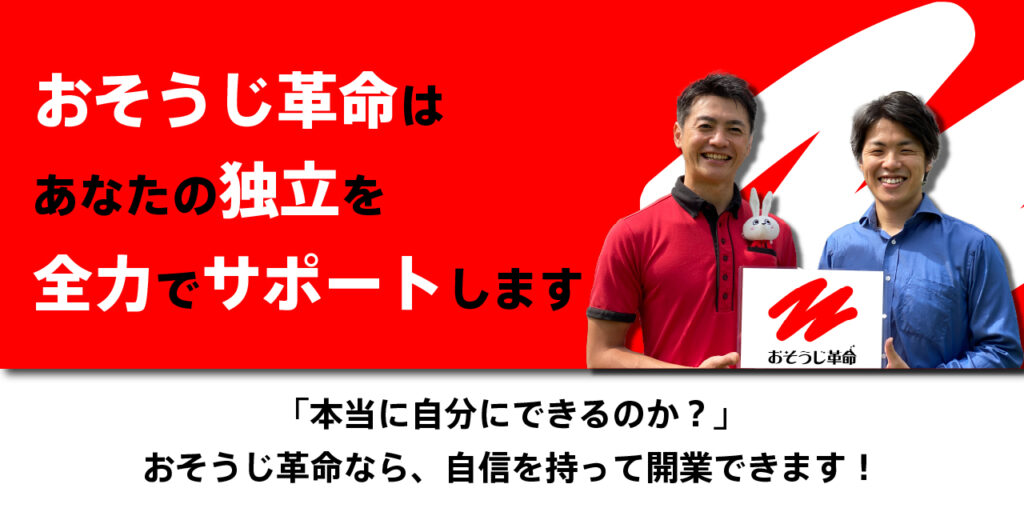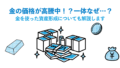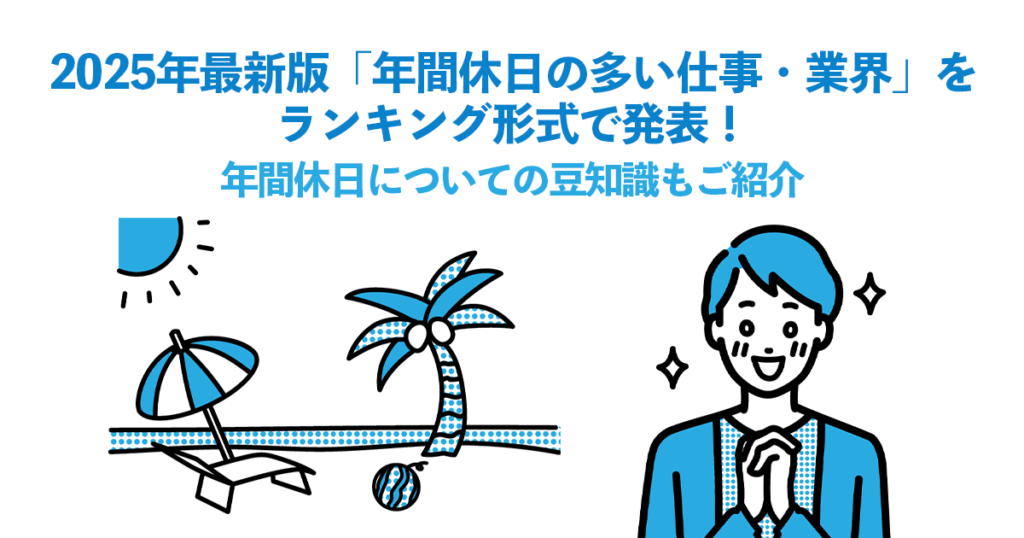
転職をする上で重視する条件は、まず「給料」、そしてその次に「休みの多さ」という方も多いと思います。
いかにお給料がよくても、休みが少なく体に負担がかかるような仕事は、なるべくなら避けたいもの。
転職するなら、ワークライフバランスがしっかりと取れるような仕事を選びたいところですよね。
では、休日が多い仕事にはどのようなものがあるのでしょうか?
また、業種や業界によって休みの日数はどれくらい違うものなのでしょうか?
そこで今回の記事では、「年間休日の多い仕事」について解説していきたいと思います。
記事の後半では、厚生労働省の資料をもとに、休日の多い仕事をランキング形式にして発表しておりますので、ぜひ最後までお読みください。
|
<目次> |

「年間休日」について知っておきたいこと
人なら誰だって、「年間休日が多い仕事」に就きたいもの。
働きづめに働いて、休みもろくにない。
そんな仕事をしたいという人は、おそらく滅多にいないことでしょう。
では、「年間休日が多い仕事」とは、具体的にどのような職業なのでしょうか?
また、年間休日とはそもそも一体どうやって決まっているのでしょうか?
有給休暇などは含まれるのでしょうか?
年間休日の多い仕事について知る前に、まずは年間休日とはいったいなんなのか知っておきたいところ。
この章では、「年間休日」についての知られざる豆知識、雑学について解説していきます。
年間休日の定義
年間休日とは、1年間に企業が定める「法定休日+所定休日」の合計日数のことを指します。
法定休日
労働基準法で定められた、会社および雇い主が労働者に必ず取得させなければならない休日のこと。
週に1回、または4週間を通じて4日以上を休日とすることが義務付けられています。
所定休日
法定休日とは別に、企業が就業規則などに則って定める休日のことです。
所定休日は企業が自由に定めることができます。
週休二日制を採用している企業の場合、二日ある休日のうち、一日は法定休日、もう一日は所定休日となります。
日本の企業の年間休日平均日数は?
厚生労働省の調査(令和5年就労条件総合調査)によると、日本企業の平均年間休日は約113日となっています。
2024年からは、働き方改革関連法の浸透により、有給取得の義務化や労働時間の上限規制が強化されました。
加えて、テレワークやフレックスタイムが普及したことで、さまざまな業界で休暇がとりやすい環境が整ってきています。
年間休日に有給休暇は含まれない!
企業が発行している求人票に記載された年間休日数には、通常「有給休暇」は含まれません。
年間休日に有給を足せば、さらに多くの休みを取得できる可能性があります。
「週休二日制」と「完全週休二日制」は違う!?
求人票をみていると、「週休二日制」と書いてある企業と、「完全週休二日制」と書かれた企業があります。
一見すると、どちらも同じ「週休二日」をうたっていますが、両者には明確な違いがあります。
- 週休二日制
月に1回以上、週2日の休みがある - 完全週休二日制
毎週必ず2日の休みがある
有給休暇の平均|有給が取りやすい業界&取りにくい業界
令和5年(実質2023年度)の有給休暇の平均取得日数は11.0日、取得率は65.3%という調査結果がでています(厚生労働省「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」より引用)。
これは、昭和59年以降で最も高い水準となっています。
また、前年と比べて取得日数も増え、取得率も前年の62.1%から向上しました。
有給の取得日数と取得率は、ともに今後も増えていくことが予想されます。
一方、業界によって有給の取得日数と取得率には大きな差があります。
取得率が高い業界(有給が取得しやすい業界)
- 電気、ガス、熱供給、水道業
取得率 73.3% - 情報通信業
取得率 65.1% - 製造業
取得率 61.6%
取得率が低い業界(有給を取得りにくい業界)
- 宿泊、飲食業
取得率 45.0% - 複合サービス業
取得率 47.4% - 卸売、小売業
取得率 48.6%
(厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」より引用)
業界ごとに有給取得のしやすさが異なるのは、業態によって人員体制や業務特性が異なるためです。
大企業やインフラ業は、従事する人が多いため、休んだ人の代わりとなる人員が確保しやすく、計画的に休みやすいという特徴があります。
一方、宿泊・飲食や小売は、業界を通して慢性的に人手不足なこともあり、有給の取得が難しい傾向にあります。
また、年中無休の業界や繁忙期変動が大きい業種、古い体質の企業文化が染み付いている会社なども、有給取得に対して後ろ向きなところが多いようです。

年間休日+有給が多い仕事・業界ランキング【2025年版】
企業や業界によって、所定休日の平均日数は異なります。
年間休日の多い仕事に就くには、各業界の休日事情を把握し、どんな業界が休みが多いのか、有給を取得しやすいのか、など、いろいろな点を比較して総合的に判断することが大切です。
では、年間休日が多く設定されている職業、および有給が取得しやすい仕事にはどのようなものがあるのでしょうか?
この章では、過去に厚生労働省から発表されたデータをもとに、年間休日数が多い仕事をランキング形式でご紹介します。
【2025年最新版】年間休日+有給が多い仕事ランキング
以下は、厚生労働省発表の資料「令和6年 就労条件総合調査」に基づき、産業別「有給休暇取得平均日数」と「推定年間休日(所定休日)」を合計し、実質的な「年間の休日総日数」が多い上位10産業をランキング形式でまとめた表です。
| 順位 | 産業(業種) | 有給取得日数 | 推定年間休日数 | 合計 (所定休日+有給取得) |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
電気・ガス・熱供給・水道業 |
13.2日 |
約106日 |
約119.2日 |
|
2位 |
製造業 |
12.9日 |
約105日 |
約117.9日 |
|
3位 |
鉱業・採石業・砂利採取業 |
12.7日 |
約105日 |
約117.7日 |
|
4位 |
情報通信業 |
12.5日 |
約104日 |
約116.5日 |
|
5位 |
学術研究・専門・技術サービス業 |
12.2日 |
約104日 |
約116.2日 |
|
6位 |
医療・福祉 |
11.0日 |
約104日 |
約115.0日 |
|
7位 |
運輸業・郵便業 |
11.1日 |
約102日 |
約113.1日 |
|
8位 |
不動産業・物品賃貸業 |
10.6日 |
約103日 |
約113.6日 |
|
9位 |
卸売業・小売業 |
10.1日 |
約103日 |
約113.1日 |
|
10位 |
金融業・保険業 |
9.9日 |
約107日 |
約116.9日 |

まとめ
今回の記事では、過去の厚生労働省データをもとに、「年間休日」についての豆知識から、各業界での有給休暇の取得状況、そして年間休日+有給取得日数の多い業界をランキング形式で解説させていただきました。
休日は、心身の健康にダイレクトに影響するとても大切な要素。
週休と生産性について調査をしたイギリスの研究(The UK’s four-day week pilot)では、61社が週20%の労働時間削減を6ヶ月実施したところ、従業員のストレスや病気が減少し、離職率も低下、生産性も維持または向上したと報告されています。
日本でも、こうした世界の研究結果報告を受け、従業員に休暇を積極的に提供するなどの先進的な取り組みを始める企業が増えています。
転職先を考える際は、休日が多い業界を選ぶのはもちろんのこと、休日・休暇について一歩進んだ考えを持った企業を調べ、選ぶことも大切と言えるでしょう。

働き方を自分で選べる!「おそうじ革命でFC独立」の魅力
企業に雇用されて働く場合、自身の休みは国が設定した「法定休日」と、就職先の企業が設定した「所定休日」とで決められるので、休日を自分で選ぶことはできません。
「もっとフレキシブルに休みたい」
「自分で休みを決めて働きたい」
そんな人には、休みが企業側に決められてしまうサラリーマンは向いていないかも。
自由度の高い働き方をしたい方には、自分の意思で働き方を選べる「独立」という選択肢がおすすめです。
ハウスクリーニングのおそうじ革命では、FC加盟店のオーナー様を常時募集しております。
おそうじ革命に加盟すれば、あなたも一国一城の主。いつを休みにするか、何時から何時まで働くか、といった就労条件は、あなたの意思で決めることができます。
時代の先をいくおそうじ革命にぜひ加盟ください!
おそうじ革命は、独自のコストカット策や研修制度など、これまでのハウスクリーニング企業とは一線を画す進歩的なビジネスモデルを構築・実践しています。
こうした取り組みが実を結び、おそうじ革命のFC加盟店は2025年8月時点で日本全国に400を超えるまでに成長しています。
独立を検討するなら、今、無二の成長軌道に乗っているおそうじ革命がおすすめ!
ぜひこの機会に、おそうじ革命の企業説明会への参加および、FC独立についての資料をご一読ください。
おそうじ革命の社員一同、熱意を持ってご対応させていただきます。