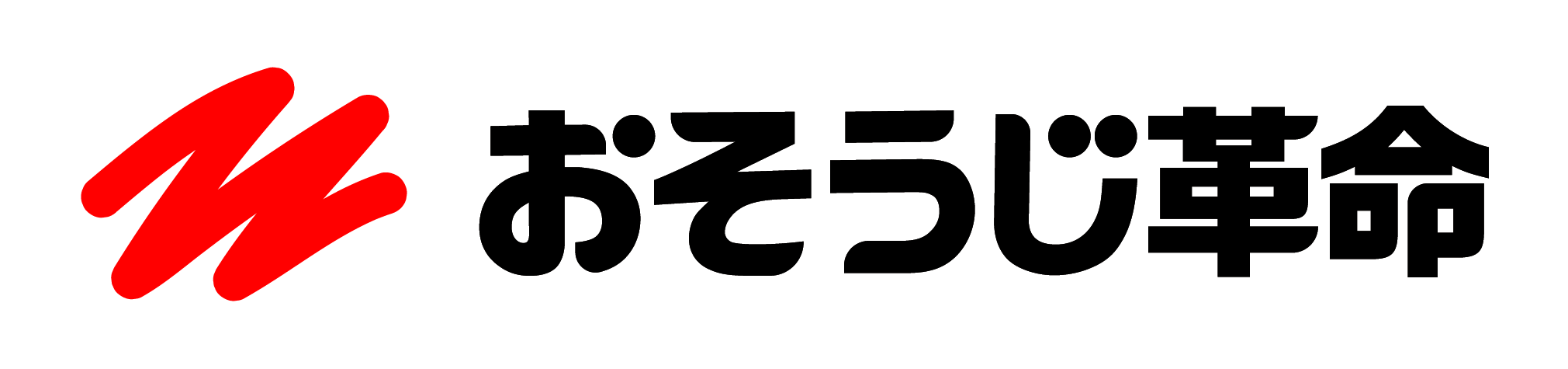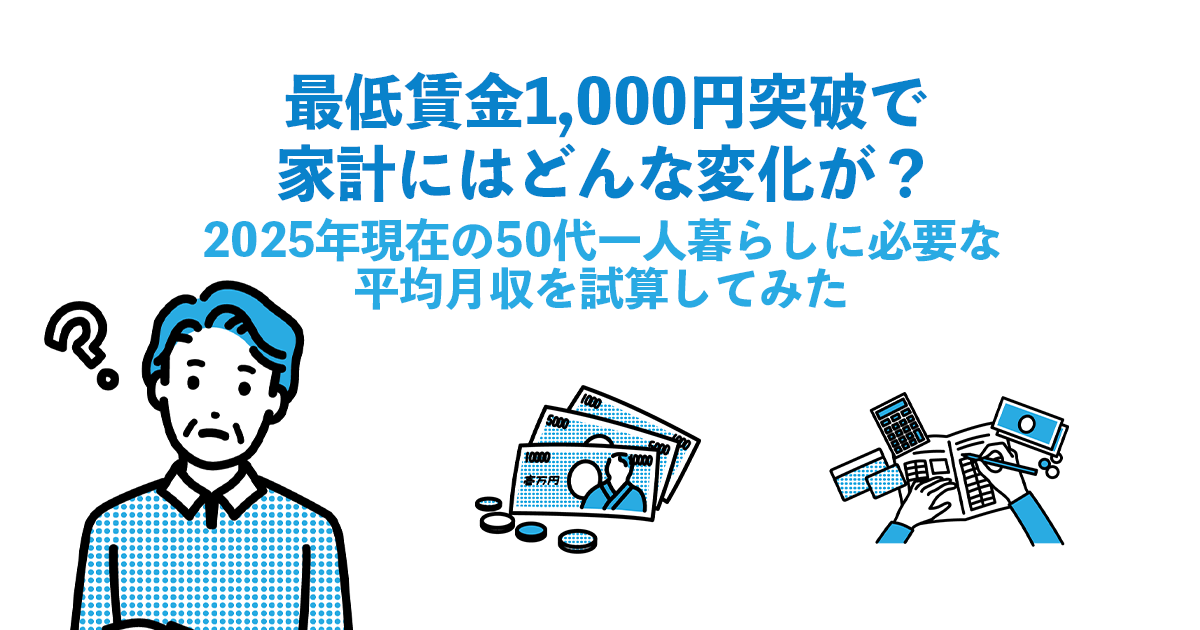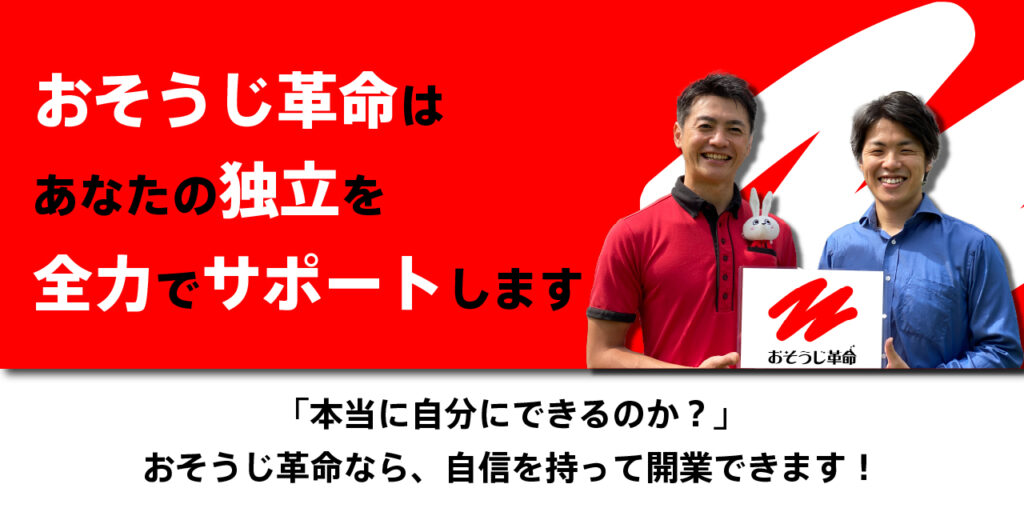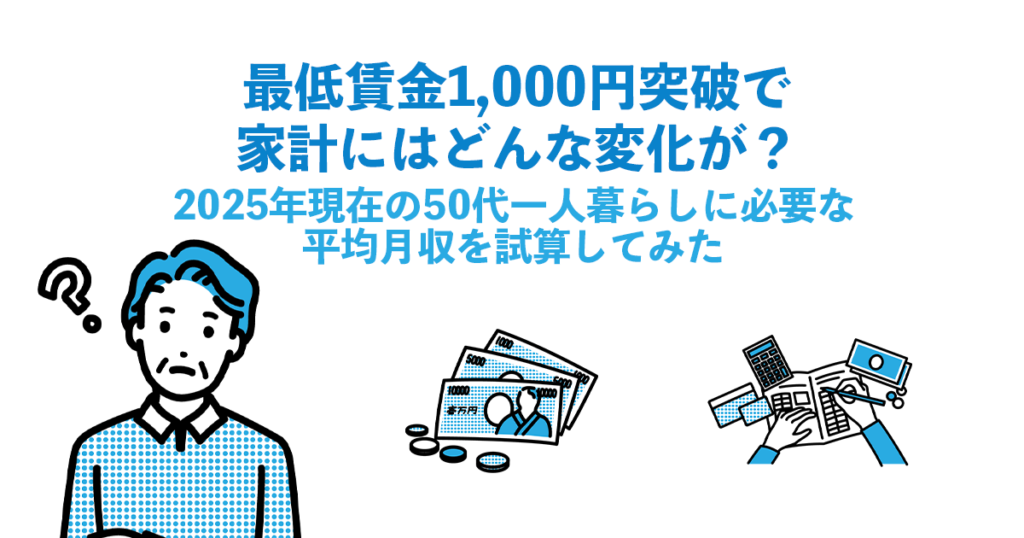
2025年、日本の最低賃金はついに「全国どこでも時給1,000円超え」の時代に入りました。
東京では1,226円、全国平均も1,121円となり、過去最高水準です。
最低賃金がアップしたことで暮らしにゆとりが生まれ、「サイドFIRE」や「早期退職からの引退生活」などを実現するハードルも低くなっており、50代以降の生活スタイルが特に多様になっていくと考えられます。
では、最低賃金が上がった今、50代以上の方が一人暮らしをする場合、月の生活費は具体的にどれくらいの金額が必要となるのでしょうか?
本記事では、50代の一人暮らしの人に焦点を合わせ、
- 最低賃金×フルタイムのリアルな手取り
- 50代一人暮らしの生活費シミュレーション
- さらに家計を余裕にするための働き方やお金の工夫
を、最新データをもとに整理していきます。
|
<目次> |

最低賃金が全国1,000円超え!フルタイムの月収はいくらに?
2025年、日本における最低賃金は、ついに全国すべての都道府県で1,000円を超えました。
最も高いのは東京都の1,226円で、全国平均は1,121円になる見通しです。
最低賃金が継続的に引き上げられている背景には、食料や光熱費といった生活必需品の値上がりが続いていることなどが挙げられます。
| 年 | 全国平均時給 (円) |
|---|---|
| 1978年 | 約315円 |
| 2005年 | 約668円 |
| 2010年 | 約730円 |
| 2015年 | 約798円 |
| 2020年 | 約902円 |
| 2021–2024年 | 930円 → 1,055円 |
| 2025年 | 1,121円 |
では、現在の最低賃金をベースに、実際にフルタイムで働いたら、月にどれくらいの収入になるのでしょうか?
この章で見ていきましょう。
1日8時間×週5日で手取りはいくら残る?
1日8時間を週5日間勤務したとして、最低賃金ベースでは手取りはどれくらいになるのでしょうか?
まずはシンプルに計算してみましょう。
月収(額面)
1,121円 × 8時間 × 21日 = 約188,000円
ここから健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税などが差し引かれます。
ざっくり2割前後が控除されると考えると、手取りは約15万円前後に落ち着く計算になります。
東京・大阪・福岡など主要都市では?
最低賃金は全国一律ではなく、地域ごとに決まります。
主要都市の時給をもとに同じ条件で試算すると次のようになります。
都市別シミュレーション
| 都市 | 時給 | 月額 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,226円 | 約205,968円 | 約16〜17万円 |
| 大阪 | 1,177円 | 約197,736円 | 約15万円前後 |
| 福岡 | 1,057円 | 約177,576円 | 約14万円前後 |
(※厚生労働省発表の資料「地域別最低賃金の全国一覧 / 令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」を元に計算しています)
最低賃金は都市部ほど時給は高くなる傾向にありますが、都会はその分家賃や物価も高いので、地方よりも生活が楽になるかといわれると、必ずしもそうではないようです。
税金や社会保険を引いた“リアルな手取り”はいくらに?
「月収20万円」と求人票に書かれていても、実際の振り込み額はもっと少なくなります。
手取りの給料から社会保険や税金が引かれるからです。
手元に残るリアルなお金はいくら?
| 月収18〜20万円 | 手取り14〜16万円 |
|---|---|
| 月収22万円前後 | 手取り17〜18万円 |
額面のお給料から保険料や税金が引かれた額は「差し引き支給額(手取り)と呼ばれます。
差し引き支給額は、業種や家族構成によって異なりますが、額面からおおよそ月収の2〜3割が差し引かれると考えておいて良いでしょう。
これを加味して考えると、最低賃金フルタイムで働いた場合の手取りは、地域差はあるものの、全国平均で14〜18万円が目安ということになります。
月ベースの収入はいくら増えた?
最低賃金が1,121円になると、フルタイム勤務(1日8時間×月21日)での月収は以下のとおりです。
| 2020年(902円) | 約152,000円(額面) |
|---|---|
| 2025年(1,121円) | 約188,000円(額面)</span |
5年間で月あたり約36,000円増えています。
月収が底上げされると…
また、月36,000円収入が増えると、暮らしには以下のようなゆとりが生まれます。
①貯蓄に回せる余力が少し生まれる
平均して月5,000円〜1万円ほど可分所得が増えるので、積立NISAやiDeCoを始めやすくなる。
②予備費や娯楽費が確保できる
急な医療費や冠婚葬祭などに対応しやすくなる。
③地方ではさらにメリットが大きくなる
家賃が安い地域では、最低賃金アップで増える家計の余裕がさらに大きくなる。

GDP2.2%成長!|2025年最新“50代一人暮らしに必要な月収”はいくら?
最低賃金がアップしたことで、5年前に比べ家計の収入は平均35,000円以上増えています。
そのため、物価高などの懸念もありますが、経済の動向は概ね堅調であり、実質GDPは年率2.2%増になるという試算が出ています(令和7年9月8日 内閣府発表)。
収入が増えたことで、家計にゆとりが生まれ、生活のハードルが徐々に下がってきいます。
この章では、50代一人暮らしの方に焦点を当て、月収いくらで生活ができるのかについて、2025年9月現在最新の情報をご紹介いたします。
家賃・食費・光熱費を合計するとどれくらい?
| 費用の目安(都市部) | 備考 | |
| 家賃 | 6万〜9万円 | ワンルーム・1K、管理費込み |
| 食費 | 約4万5,000円 | 単身世帯平均 物価上昇でさらに増加傾向 |
| 光熱費 | 1万5,000〜2万円 | 電気・ガス・水道の合計 |
| 合計 | 12万〜15万円程度 |
【結論】「フルタイム×21日」で十分生活可能!
最低賃金がアップしたことで、手取りの金額も増え、その結果、50代一人暮らしの方も一昔前に比べ生活のハードルが徐々に低くなってきています。
以下は、平均最低賃金から計算した月収の例。
これを見れば、月21日フルタイムで働けば、一人暮らしに必要な12〜15万円の収入を賄えることがわかります。
| 月収の額面 | 控除後の手取り額 | |
|---|---|---|
| フルタイム(21日勤務) | 1,121円 × 8 × 21 = 約188,000円 | 約150,000円〜155,000円 |
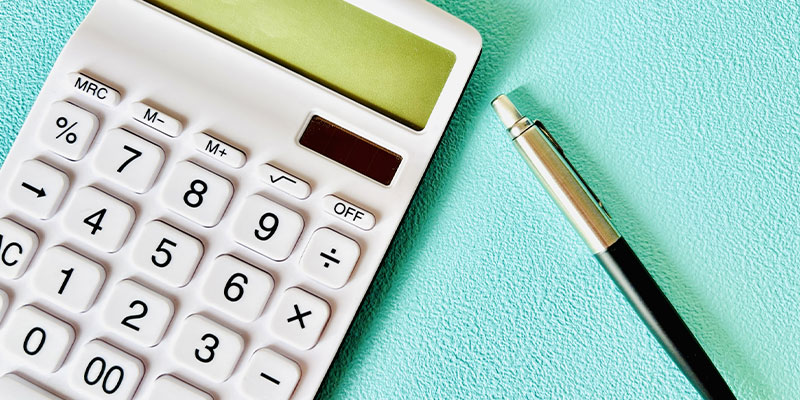
さらに余裕のある暮らしをするには?|50代からの働き方と暮らしの工夫
上の章では、50代一人暮らしの方に必要な1ヶ月分の生活費と、その金額を稼ぐためにどれくらい働く必要があるのかについて解説させていただきました。
諸々試算したところ、月21日フルタイムで働けば、生活に必要なお金は賄うことが可能という結果に。
ただし、これはあくまでも「最低限」の生活に必要なお金です。
もっと余裕のある暮らしがしたい!という方は、本業でお金を稼ぐのに加えて、収入を増やす施策を生活の中に取り入れることが必要となります。
この章では、50代一人暮らしの方におすすめの「プラスαの収入を増やすテクニック」や、「働き方」について解説していきます。
フル勤務がきつい人におすすめ「週4+副業」スタイル
50代になると、体力面や家庭の事情でフルタイム勤務を続けるのが難しい、という方も少なくありません。
そんな方におすすめなのが 「週4日勤務+副業」 という働き方です。
- 週4日をパートや契約社員で働き、基礎的な生活費を確保
- 残りの時間で在宅ワークや短時間のアルバイトを組み合わせて収入を補う
- 配送や警備などの体を動かす仕事と、事務やオンライン業務を組み合わせると、健康的にも良い、バランスの取れた働き方ができる
このように働き方を分散させると、精神的な負担も軽くなり、収入のリスクヘッジにもつながります。
時給アップにつながる職種・時間帯
同じ労働時間でも、職種や時間帯の選び方次第で収入は変わります。
- 深夜&早朝シフト
コンビニや清掃業などは深夜割増で時給25%アップ - 介護&警備&ドライバー
人手不足の業界では50代以上も歓迎され、平均より高い時給がつきやすい - 専門スキルを活かす仕事
パソコンスキルや資格(簿記、電気工事士、調理師など)があると、一般的なアルバイトより高単価で働ける
「自分が続けやすい時間帯」と「需要の高い職種」を組み合わせると、より高い収入を得ることも可能になります。
資産や貯金を運用する
最近では、投資信託や積立NISAなどの金融商品を活用した資産運用の運用益で生活費を補填する人も増えています。
金融商品には、以下のようなものがあります。
- 投資信託
本人に代わって、専門家が株や債券などに投資し運用益を稼ぐ。 - NISA(少額投資非課税制度)
年間投資額に上限がある代わりに、運用益や配当が非課税になる制度。 - iDeCo(個人型確定拠出年金)
掛金が全額所得控除になり、老後資金を自分で積み立てる私的年金制度。
起業を検討するのもおすすめ
「これまでの働き方では満足できない」「もっと自由に稼ぎたい」という方には、起業という選択肢もあります。
第二の人生は新しいチャレンジにもってこいの時期
50代は経験や人脈が豊富で、若い頃にはなかった強みを活かしやすい年代。
また、子どもが独り立ちするなど、家計的な負担が軽くなる時期でもあります。
リスクを恐れず挑戦するには良いタイミングです。
働けば働くだけ結果が返ってくる
起業をすれば、会社員と違い、ビジネスへの努力や工夫がそのまま成果に直結します。
時間の使い方も自分で決められるため、やりがいを感じやすいのも特徴です。
ライバルが少ない市場で戦える
ビジネスの世界は競争が激しいと思われがちですが、実は業種や業態、地域によっては、大きなニーズがあるにもかかわらず競合が少ないなど、チャンスが眠っている分野も多数あります。
その上、フランスやイギリスでは8人に1人が起業しているのに対し、日本の起業率は約5%にとどまっているなど、日本では起業する人が極端に少なく、ライバルも必然的も多くないので、個人でも十分にやっていける可能性があります。

50代 × 1人暮らしの皆さんにおすすめ!おそうじ革命で起業
弊社ハウスクリーニングのおそうじ革命では、FCオーナー様を随時募集しております。
おそうじ革命のハウスクリーニングサービスは、業界でも最長クラスの研修期間に加え、独立後も本部が経営をサポートする体制を整えております。
本部は加盟店の“共同経営者”
ただ看板とノウハウを貸すだけのFCチェーンが多いのに対し、おそうじ革命は、オーナーと本部が加盟店の「共同経営者」というスタンスを貫き、一店一店に経営者として真剣に取り組んでいます。
おそうじ革命FCチェーンのオーナー様からは、「開業後も安心して経営にあたれた」、「相談しやすい空気があって助かる」といったお声をたくさん頂戴しております。
自分のペースでフレキシブルに働ける
おそうじ革命のFCでは、多様な働き方ができることも魅力です。
オーナー様には、
- 法人の一部門として加盟
- 複数の出資者からなる合弁会社として加盟
- 深夜帯の現場(工場や駅、空港など)をメインに活動
- 土日を中心に営業
などなど、さまざまな形式・形態で加盟されている方が多数いらっしゃいます。
おそうじ革命のFCチェーンでは、定休日や営業時間を自分で自由に設定することができるため、ご自身のライフスタイルに合わせてフレキシブルに働くことができます。
約2ヶ月間の研修 + 開業後の手厚いサポート
おそうじ革命では開業にあたって、約2ヶ月間という研修期間を設定しています。
この日数は、ハウスクリーニング業界においても異例の長さです。
しかしながら、ハウスクリーニングの技術は、習得にそれなりに時間がかかるものです。
それを短期間で詰め込み教育しても、付け焼き刃程度の技術・知識しか身につきません。
サービスマンとして未熟な状態で独立をしたところで、経営が上手くいくはずはなく、事実、大手のハウスクリーニングFCチェーンの廃業率は5年で50%といわれています。
おそうじ革命はこうした事態を避けるため、開業前の技術研修にしっかりと時間を割いています。
独立するのは少し遅くなりますが、ちゃんとした技術を身につけてからお店を出せるので、独立後も安定した経営を続けられる可能性が高まります。
加えておそうじ革命では、経営がうまくいかない加盟店へ、経営についてのアドバイスや案件の紹介など、さまざまなサポートをご用意しております。
独立して悠々自適に暮らす50代のオーナー様多数!
おそうじ革命のオーナー様の中には、50代で会社を早期退職し、退職金を元手にFC加盟店を出店された方が多数いらっしゃいます。
その中には、1人暮らしで個人事業主となり、平日は仕事、休日は遊びに、と、独身生活を大いに謳歌されている方もたくさんいます。
「50代で新たなチャレンジをしてよかった」
「会社員時代よりも自由で、自分の意思で生きている実感があります」
「再就職も考えたけど、独立して正解でした。余裕もあるし、毎日楽しいです」
50代で活躍されるオーナーさんからは、以上のような声も多く、皆さんご自身の選択を肯定的にお考えのようです。
ライフステージが大きく変わる50代は、自由な生活を手にするビッグチャンス!
ぜひこの機会に、おそうじ革命の企業説明会への参加および、FC独立についての資料をご一読ください。
おそうじ革命の社員一同、熱意を持ってご対応させていただきます。